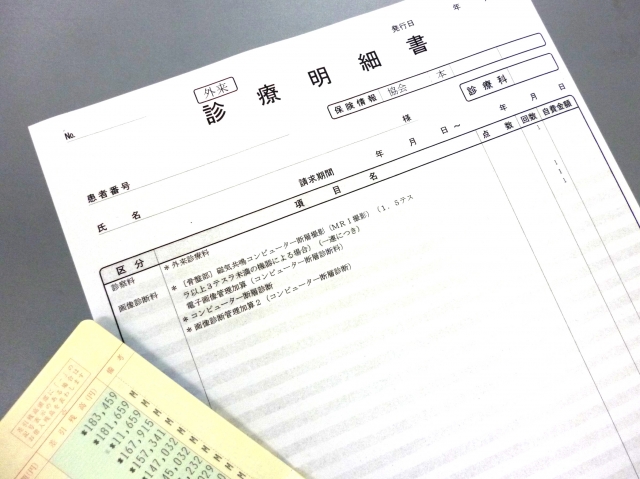こんにちは、ポワロです。
2021年11月1日放送の『逆転人生』で、『医療情報の公開・開示を求める市民の会』代表の勝村久司(かつむら ひさし)さんが紹介されます。
勝村久司さんは1990年12月、陣痛促進剤被害で長女を出生9日後に亡くしました。
それをきっかけに、医療裁判や市民運動に取り組むようになりました。
しかし、一般市民が医療業界を相手に闘うことには数々の困難があったことでしょう。
今回は勝村久司さんの医療情報公開や薬害被害などに関する取り組みについて調べてみました。
勝村久司さんの目指す患者本位の医療とは?
勝村久司さんは長女を薬剤被害で失いました。
このような場合に被害者が取れる行動としては、泣き寝入りか裁判で争い、真実を明らかにするかの二者択一になると考えられます。
勝村久司さんは後者の裁判を選びました。
しかし、この医療事故の裁判において、被告である医療者側のカルテ改ざん、口裏合わせなどの不誠実な対応によって、なぜ子供が死ななければならなかったのか、なぜ詳しい説明がないのかといった真実を明らかにすることが非常に難しいということを身をもって感じることになりました。
また、1990年の頃にはガン患者に対して医師が病名を知らせないという行為があたりまえのように行われていました。
勝村久司さんは、このような医療界の事故や真実を隠そうとする隠ぺい体質が問題だと考えています。
隠すのではなくて、事故の原因分析をして再発防止につなげていくシステムを医療界で構築してほしいと願っているのです。
勝村久司さんは医療界に正直文化を育てることによって、患者本位の医療につながっていくと考えているのでしょう。
勝村久司さんの医療情報公開への闘いの経歴
陣痛促進剤の無理な投与で長女を亡くした勝村久司さんは病院を相手に裁判を起こしますが、一審では完全敗訴してしまいます。
なぜ医療裁判では勝てないのかを追求することで、そのからくりを明らかにし、粘り強く戦った結果、二審で逆転勝訴を勝ち取ることができました。
この医療裁判の記録は下記の著書に詳しく書かれていますので、興味のある方は読んでいただければと思います。
単なる裁判記録というだけでなく、日本の医療が改善していく歴史に残る名作ではないでしょうか。
ぼくの「星の王子さま」へ 医療裁判10年の記録 (幻冬舎文庫)
この医療裁判をきっかけに、勝村久司さんは医療事故や薬害に関する市民活動に取り組んでいくことになります。
その活動の中で、勝村久司さんが重要だと考えているのは、医療を専門家任せにせずに、市民が主体的にチェックすることと、それを可能にするための情報公開です。
要するに民主主義という本来ならあたりまえのことができていなかったから、改善していこうということなんです。
勝村久司さんが関わった活動の主な成果として、以下のようなものがあります。
・1996年 『医療情報の公開・開示を求める市民の会』という市民団体を設立
カルテ・レセプト開示、自治体や国の医療に関する情報の公開等を求めてきた。
・2015年10月より国において医療事故調査制度が施行された
医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うための組織として医療事故調査・支援センタ-を設けた。
厚生労働大臣により、一般社団法人 日本医療安全調査機構が医療事故調査・支援センタ-として指定されている。
勝村久司さんのプロフィール
勝村久司さんは1961年生まれ。
大阪府立牧野高等学校、京都教育大学理学科を卒業し、高等学校地学教諭を務めました。
天文学が専門で、自然科学を学んだ勝村久司さんにとっては、物事の真実を知ること、何故そうなるのかといったことを客観的な証拠をもとに追求していくアプローチが身についていると思います。
我が子が何故死ななければならなかったのかという原因を、裁判での証言や資料を整理、解釈して明らかにしようとする姿勢にそれがよく表れています。
そして、「医療被害を受けた人が頑張っている理由は、被害を繰り返させないため、被害者の人権を回復させるためである」という信念に基づいてさまざまな活動に取り組まれています。
【主な著書】
『ぼくの「星の王子さま」へ~医療裁判10年の記録~』(幻冬舎)
『レセプト開示で不正医療を見破ろう!』(小学館)
『患者と医療者のためのカルテ開示Q&A』(岩波書店)
まとめ
今回は、『医療情報の公開・開示を求める市民の会』代表の勝村久司さんについて調べてみました。
- 勝村久司さんは1961年生まれ。大阪府立牧野高等学校、京都教育大学理学科を卒業し、高等学校教諭を務めました。
- 1996年 『医療情報の公開・開示を求める市民の会』という市民団体を設立
カルテ・レセプト開示等の情報公開を求めてきました。 - 勝村久司さんは医療事故の原因分析をして再発防止につなげていくシステムを医療界で構築してほしいと願っています。
30年に渡る経験を活かして、今後も患者本位の医療の実現に向けてますますご活躍されることを期待したいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【この記事を読んだ方におススメの記事はコチラ】